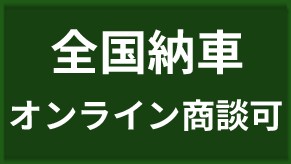はじめに
スカイラインGT-R R32。日本国内では「平成の怪物」と称されましたが、世界に出たとき、その存在はさらに大きな異名を与えられることになりました。それが「Godzilla(ゴジラ)」です。呼び名はただのニックネームではなく、R32がどのように受け入れられ、どんな文化的影響を与えたかを物語る証。今回は海外Wikipediaを参照しながら、30〜50代のクルマ好きが胸を熱くするような海外での呼び名とその背景にある逸話やトリビアを、マニアックに掘り下げて紹介していきます。

1. 「Godzilla」誕生の瞬間
-
由来は1990年、オーストラリアの自動車雑誌『Wheels』誌。
-
バサースト1000で圧倒的な速さを見せつけたR32を「日本からやって来た怪獣」と表現。
-
以後、現地ファンもメディアもGT-Rを“Godzilla”と呼び続け、R32だけでなく後継モデルにまで受け継がれることに。
エピソード:地元の観客が「またゴジラが勝った」と嘆く姿が新聞記事に掲載され、異名は完全に定着した。
2. 「日本の戦車(Japanese Tank)」
-
ドイツや欧州の一部メディアは、その堅牢なボディと圧倒的なトラクション性能から「ジャパニーズ・タンク」と呼んだ。
-
これは揶揄であると同時に、耐久性へのリスペクトの表現でもあった。
トリビア:ニュルブルクリンク24時間レースでの堅実な走りが、この呼び名を後押しした。
3. 「怪物(Monster)」と呼ばれた理由
-
欧米メディアではしばしば「Monster Skyline」と表記された。
-
ストレートスピード、電子制御四駆、ツインターボという組み合わせが、既存の欧州車を圧倒。
-
「怪物」という表現は決して誇張ではなく、レース結果そのものが裏付けていた。
4. アメリカでの「Forbidden Fruit(禁断の果実)」
-
アメリカでは1990年代の輸入規制によりR32は正規導入されず、ファンから「Forbidden Fruit」と呼ばれた。
-
雑誌『Car and Driver』は「最もアメリカ人が羨む、日本国内専用の怪物」と紹介。
-
輸入解禁後、一気に人気が爆発したのも、この“幻の存在”としての神秘性による。
5. 海外広告・記事での呼称
-
英国広告では「Porsche 911を超える存在」として“Godzilla”を逆手に取ったコピーが使われた。
-
豪州新聞『Sydney Morning Herald』は「フォードとホールデンの戦争を終わらせた怪物」と書き立てた。
-
日本国内のカタログでは「怪物」の呼び名は避けられたが、海外では逆に誇張して活用されたのが興味深い。
6. ファン文化と愛称
-
オーストラリアでは「ゴジラミーティング」と呼ばれるオーナーズクラブイベントが毎年開催。
-
北米では「Godzilla」ロゴ入りのステッカーやTシャツが人気を博す。
-
ニックネームが単なる呼称に留まらず、ファンアイデンティティの象徴になった。
まとめ
R32 GT-Rは「Godzilla」という呼び名によって、日本国内のヒーローから世界の伝説へと変貌しました。異名には驚きや皮肉、そして畏敬が込められており、それぞれの地域がGT-Rをどう見ていたかを如実に物語ります。
30〜50代のクルマ好きにとって、その呼び名を知ることは、単なる雑学以上に、かつてのレース熱狂をもう一度味わうことなのです。