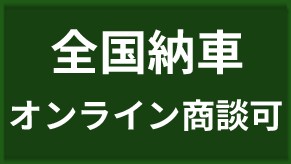R32 スカイラインGT-Rのレース実績|“勝つための市販車”が、世界の秩序を揺らした4年間
R32スカイラインGT-Rの魅力は、速さの数字だけでは語り切れません。あのクルマがサーキットで見せたのは、もっと生々しい「勝利の必然」でした。レースの現場は、言い訳が一切きかない世界です。そこでR32は、技術でねじ伏せ、結果で黙らせ、ついには“ルールそのもの”の空気を変えてしまった――そんな稀有な存在でした。ウィキペディア+1この記事では、海外Wikipedia(英語版)を参照しつつ、「R32スカイラインGT-Rのレース実績」を、トリビアと逸話込みでマニアックに整理します(読みやすさと検索性を意識して構造化しています)。この記事の要点(先に結論)日本のツーリングカー選手権では、1990〜1993年にシリーズ4連覇、さらに参戦29戦29勝という“無敗の数字”を残しました。ウィキペディアオーストラリアでは、1991年にジム・リチャーズ、1992年にマーク・スカイフがR32でシリーズ王者を獲得しています。ウィキペディア+2ウィキペディア+2バサースト1000では、1991年に勝利し、1992年は豪雨と赤旗の混乱の中で連覇。勝ったのに祝福されない、レース史でも異様に感情が揺れた結末が残っていま...