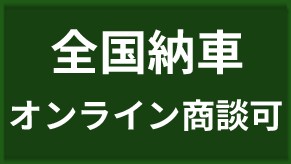「伝説の系譜を終わらせるな」──最後のGT-Rに課せられた使命
1999年、R34スカイラインGT-Rは、時代の荒波の中で生まれた。
排ガス規制や安全基準が厳しさを増し、ハイパフォーマンスカーが次々と姿を消す中で、GT-Rブランドの存続は危ぶまれていた。
しかし日産の開発陣は決して諦めなかった。彼らはこう語った。
「伝説は終わらせない。ただし“懐古”ではなく、“進化”として次の章を刻む。」
R32が無敗神話を築き、R33が世界基準を押し上げた。その系譜を継ぐR34は、「最終進化系」として、単なる“速い車”ではなく「戦うための兵器」として設計されたのだ。

I. 新時代のGT500マシン──JGTCでの戦いが示した「電子制御の力」
R34が最も輝いた舞台、それが全日本GT選手権(JGTC)GT500クラスだった。
1999年、NISMO、カルソニック、ペンズオイルといった名門チームがR34を投入すると、マシンはデビュー戦から異次元の走りを見せた。
心臓部は熟成の極み「RB26DETT」。ただし、出力だけで勝負する時代は終わっていた。R34は空力、電子制御、そしてドライバビリティのすべてを統合した「総合性能マシン」として開発されていたのだ。
特に注目すべきはATTESA E-TS ProとアクティブLSDの組み合わせ。
これにより駆動力の最適配分が劇的に向上し、コーナー立ち上がりでのトラクション性能はライバルのNSXやスープラを凌駕した。
「R34は速さだけでなく、“走りの質”が違っていた。ラインを外しても即座に修正が効く。まるでマシンが意志を持っているようだった。」
──星野一義(カルソニックチームインパル)
📊 1999〜2002 JGTC主な戦績(GT500)
| 年 | チーム名 | 主な勝利・タイトル |
|---|---|---|
| 1999 | ペンズオイル・ニスモGT-R | 鈴鹿300km・富士500km優勝、シリーズ2位 |
| 2000 | カルソニックGT-R | 菅生・富士優勝、年間3位 |
| 2001 | ペンズオイルGT-R | 開幕戦優勝、チャンピオン争いに終盤まで絡む |
| 2002 | モチュールピットワークGT-R | 最終年、富士で2位フィニッシュを飾る |
4年間で複数勝利を重ね、シリーズチャンピオンには届かなかったものの、常に優勝争いの中心にいたことがR34の実力を証明している。
II. 戦場は海の向こうへ──R34とル・マン耐久の夢
R34の戦いは日本国内にとどまらなかった。
2000年、日産と英国の名門「Ray Mallock Ltd(RML)」は、R34をベースとした耐久仕様マシンを制作。ル・マン24時間レースを視野に入れたテストプログラムを開始する。
このマシンは、従来の4WDからFRへと駆動方式を変更。空力も一から見直され、長距離を走り抜く冷却性能と整備性を備えていた。
RB26は耐久用にデチューンされ、出力は約480psと控えめながら、24時間走り切るための信頼性が重視された。
残念ながら、R34そのもののル・マン本戦参戦は幻に終わったが、このプロジェクトで得られた技術は後のR35 GT-R LM NISMOへと受け継がれていく。
「あの頃の挑戦がなければ、欧州でのGT-Rの戦いは生まれなかった。」
──元日産モータースポーツ部門エンジニア・田嶋健一
III. スパ24時間で見せた「不屈の魂」
R34の存在感を世界に知らしめたもう一つの戦いが、スパ・フランコルシャン24時間耐久レースだ。
2001年、プライベーターの「Team Falken」がR34 GT-Rを投入。FIA GT選手権に準じた仕様で、ヨーロッパ勢に挑んだ。
結果は総合6位という好成績。ポルシェやフェラーリといった名門GTマシンがひしめく中で、この結果はまさに“快挙”だった。
「R34は壊れない。タイヤが削れても、ブレーキが焼けても、走ることをやめなかった。」
──チームメカニック・ヨハン・マルテンス(2001年スパ戦後コメント)
このレースで得られた耐久データは、後のGT-R NISMOモデル開発にも反映されていく。量産車の枠を超えて戦うマシンとして、R34はその可能性を大きく広げたのだ。
IV. プライベーターの情熱──世界中で生まれた“もうひとつのR34伝説”
R34はワークスだけのマシンではなかった。
そのバランスの取れたシャシーと信頼性の高いRB26は、世界中のプライベーターにとって理想の素材だった。
ニュージーランドではGT選手権でR34が活躍し、地元チーム「Team DJR」がシリーズチャンピオンを獲得。
オーストラリアでは、ドラッグレースやタイムアタックシーンで900psオーバーのR34が次々と登場した。
イギリスでは「Middlehurst Motorsport」がR34をチューニングし、ブランズハッチやシルバーストーンで開催された耐久イベントに出場。重量級マシンでありながら、FR勢を抑えて表彰台を獲得した記録も残っている。
「GT-Rはチューナーの想像力を刺激する“素材”だった。R34はその頂点だ。」
──HKSヨーロッパ代表・リチャード・ロイド
V. 現地観客と海外メディアの声──「R34は日本車の哲学そのもの」
R34はそのレース実績以上に、観る者の心を動かす存在でもあった。
2000年代初頭、鈴鹿や富士でGT500マシンとして走るR34を見た観客は、その姿をこう表現している。
「あれは単なるレースカーじゃない。“意志”を持って走っているようだった。」
──当時の鈴鹿来場者・インタビューより
欧州メディア『Evo』誌は、2001年のスパ耐久参戦をこう評した。
“It is not the fastest, not the most expensive. But it is the purest expression of Japanese racing spirit.”
(最速でも、最も高価でもない。だがそれは、日本のレーシングスピリットそのものだった)
この評価が象徴するように、R34は“数字では測れない価値”を持つマシンだった。
それは、勝利数や表彰台の数だけでなく、走りの哲学そのものを体現していたからだ。
VI. 戦いの果てに遺したもの──R35へと受け継がれるレガシー
2002年、R34はJGTCの戦場から姿を消した。
同時に「スカイラインGT-R」という名も歴史に幕を下ろし、GT-Rは次のステージへと進むことになる。
だが、R34が遺した戦いの記憶は消えない。JGTCで磨かれた電子制御技術、耐久レースで培われた冷却・空力ノウハウ、そして世界中のチューナーが示したポテンシャルの高さ──
それらすべてが、R35の開発に直接的な影響を与えている。
R34は“最後のGT-R”であると同時に、次のGT-Rを生み出すための最終テストマシンでもあったのだ。
終章:「勝つためだけに生まれたわけではない」──R34という存在の本質
R34の戦績を数字だけで見れば、R32のような圧倒的無敗神話は存在しない。
だが、それは本質ではない。R34が戦い続けた4年間は、勝利のためだけではなく、未来のGT-Rの礎を築くための時間だったのだ。
JGTCでの激闘、スパ24時間の完走、プライベーターたちによる挑戦──
それらはすべて、R34が「公道からサーキットまで一貫した思想を持つマシン」であることを証明する歴史である。
“最後のスカイラインGT-R”は、単なる終着点ではなかった。
それは「未来への跳躍台」として、GT-Rという名を次の時代へと送り出す使命を果たしたのだ。
そして今なお、多くのファンがこう語る。
──「R34こそ、GT-Rが“哲学”だった時代の最後の証明だ」と。
💡関連動画💡