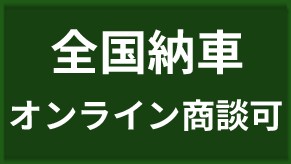「スカイラインの延長ではない」──R35が掲げた“革命”
2007年。
東京モーターショーの舞台でその姿を現した瞬間、日本中のカーファンが息をのんだ。
それは、かつての「スカイラインGT-R」の延長線上にはいない“まったく新しい存在”──Nissan GT-R (R35) だった。
それまでGT-Rは、あくまで「スカイライン」という量産車をベースにした高性能バージョンという位置付けだった。
しかしR35は違った。社内でも「これはスカイラインではない」と明言され、ゼロから“世界最速”を目指すプロジェクトとして開発が始まったのだ。
日産が掲げたのは、たった一つの目標。
「フェラーリ、ポルシェ、ランボルギーニ──そのすべてを、量産車として超える。」
これは単なるスローガンではなかった。日本メーカーが“世界基準”を真っ向から打ち破る挑戦だったのだ。

I. 「ポルシェに勝て」──GT-R開発チームの合言葉
開発の中心にいたのは、当時のチーフ・プロダクトスペシャリスト、水野和敏。
彼がプロジェクトを引き継いだとき、最初に口にした言葉がすべてを象徴している。
「ポルシェ911ターボに勝てなければ、GT-Rではない。」
その“標的”は明確だった。911ターボという欧州スポーツカーの象徴を超えなければ、世界は振り向かない。
日産は、エンジンから駆動系、シャシー、ボディ構造に至るまで、既存の技術をすべて捨て去り、新しいGT-Rを一から作る道を選んだ。
たとえば心臓部となるエンジン。従来の直6から完全に決別し、3.8L V6ツインターボ「VR38DETT」を新開発。
しかもすべてが職人の手によるハンドビルドで、各エンジンには組み立てを担当した匠のプレートが刻まれた。
さらに駆動系には、当時量産車としては極めて異例のトランスアクスルレイアウト+デュアルクラッチトランスミッションを採用。
エンジンはフロント、トランスミッションとデフはリアに配置し、前後重量配分の最適化とトラクション性能の向上を両立した。
「GT-RはもはやFRでも4WDでもない。“GT-Rレイアウト”だ。」
──水野和敏
II. 「ニュルの壁」──世界最速への戦いと“7分38秒”の衝撃
開発陣が「世界最速」を証明するために選んだ舞台は、聖地・ニュルブルクリンク北コースだった。
この全長20.8kmの過酷なサーキットで速さを証明しなければ、真のスーパースポーツとは呼ばれない。
2007年のプロトタイプ段階で、GT-Rは7分38秒54という驚異的なラップタイムを記録。
これは当時の911ターボ(997型)を凌駕し、世界中の自動車メディアを震撼させた。
“A Japanese car just humbled Porsche on its own turf.”
(日本車が、ポルシェの“庭”で屈辱を与えた)
──英『Top Gear』誌(2007年)
ポルシェは公式に異議を唱え、「GT-Rのテスト車は市販仕様ではない」と発表する事態にまで発展した。
だが日産は市販車そのもので記録を叩き出しており、GT-Rが“本気”で世界を狙っていることを証明したのである。
III. 「コンマ1秒の執念」──R35が生んだテスト地獄
R35の開発現場は、日産史上もっとも過酷なものだったといわれる。
たとえばニュルだけでも、20,000km以上の耐久走行を実施。ブレーキやサスペンション、トランスミッションは何度も破損し、そのたびに改良が繰り返された。
ブレーキ開発では、ブレンボとの共同で6ピストンキャリパー+390mmローターという当時としては破格の構成を採用。
サスペンションにはビルシュタイン製ダンパーをチューニングし、ニュルの凸凹路面でも安定して走れる“世界基準”の脚を与えた。
そして最も象徴的なのが、空力パッケージだ。
GT-RのCd値(空気抵抗係数)はわずか0.27。それでいて強大なダウンフォースを発生し、300km/h超の速度域でも抜群のスタビリティを確保した。
「コンマ1秒を削るためなら、ドアミラーの形さえ変える。」
──開発チームのスローガン
IV. 「量産車なのにスーパーカー」──“毎日乗れる最速”という新しい概念
R35が生んだ最大の革命は、「スーパーカー=非日常」という常識を覆したことだった。
フェラーリやランボルギーニが“非日常の象徴”として存在していたのに対し、GT-Rは普段使いできるスーパーカーという新しい価値を提示したのだ。
・雨の日でも安心して踏める電子制御トルク配分
・街乗りでも快適な乗り心地と静粛性
・大型トランクと4人乗りの実用性
「世界最速」を目指しながら、“毎日使える”という日常性まで捨てなかったのはGT-Rだけだった。
“The GT-R is a supercar that doesn’t punish you for driving it.”
(GT-Rは、乗る者を罰しないスーパーカーだ)
──米『Car and Driver』
この“実用スーパーカー”という発想は、後にマクラーレンやポルシェが採用する方向性にも影響を与えたといわれている。
V. 「進化を止めない」──R35が刻んだアップデートの哲学
R35の真髄は、発売後も進化を止めなかったことにある。
初期型(2007年)の480psから始まり、2011年モデルでは530ps、そして最終型2022年のNISMOでは600psへと出力を拡大。
0-100km/h加速は3.5秒から2.5秒台へと進化し続けた。
なかでも象徴的なのが、**2011年モデルの“第二世代R35”への進化だ。
ブースト圧や点火時期、ECUの制御マップを徹底的に見直し、空力パーツの細部までも再設計。
これにより、GT-Rは単なる年次改良ではなく、「進化するマシン」**としての地位を確立した。
「R35は“完成したクルマ”ではない。“進化を続けるプロジェクト”なんだ。」
──元GT-Rチーフエンジニア 水野和敏
VI. “GT-Rを超えるGT-R”を作る──NISMOと匠たちの闘い
2014年、R35の究極進化形として登場したのがGT-R NISMOだ。
ニュルブルクリンクでのタイムは7分8秒679──量産車として世界最速級の記録であり、GT-Rが再び頂点に返り咲いた瞬間だった。
その裏には、タカミ・ファクトリーと呼ばれる匠の手仕事がある。
NISMO用のVR38エンジンは、標準モデルよりさらに厳格な手組み工程を経て組み立てられ、1基ずつ異なる“音”と“鼓動”を持つとさえ言われる。
サーキット専用モデル「GT-R NISMO N-Attack Package」は、ニュルでの実戦データをフィードバックし、サスペンションや空力パーツがレース由来のものへと変更された。
“This is not a tuned GT-R. This is the ultimate expression of GT-R.”
(これはチューニングカーではない。GT-Rという思想の究極形だ)
──独『Sport Auto』
VII. 終章:「スーパーカーを民主化したマシン」──R35が残したもの
R35は“奇跡のクルマ”と呼ばれることがある。
それは、スーパーカーという概念を「富裕層のもの」から「走りを愛するすべての人のもの」に広げたからだ。
1000万円台でフェラーリやポルシェと肩を並べるパフォーマンス。
毎日使える快適性と、伝統を捨て去ってでも突き詰めた速さ。
そして、**「量産車で世界最速」**という確固たる事実。
R35は、日産が世界に突きつけた“日本の答え”だった。
そしてこのマシンの系譜は、単なる後継車開発を超え、「R36」という次の挑戦へと受け継がれていく。
R35が残したのは、記録ではなく“哲学”──
それは、「本気で世界と戦うなら、常識などいらない」という、不変の信念である。