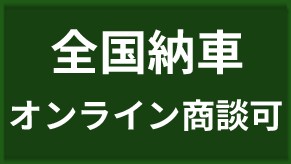- はじめに
- 1. “ゴジラ”の名付け親は英国の雑誌編集者
- 2. 開発プロジェクト名は「PGC10」
- 3. 伝説のRB26DETTエンジン誕生秘話
- 4. “ハイブースト”の誕生は社内ライバル対決から
- 5. フルタイム4WD「ATTESA E-TS」の裏側
- 6. 軽量化のための“ウィンドウテスト”
- 7. “カーボン”流用の苦悩と栄光
- 8. ピットロードからフィードバックされたエアロデザイン
- 9. “セミセルフレベリング”サスペンションの試作
- 10. 開発スタッフの愛機は「初代GT-R」だった!?
- 11. 海外テスト走行で露呈した“寒冷地問題”
- 12. “電子制御”4WDのチューニング秘話
- 13. サーキットのフィードバックが市販車に直結
- 14. 開発終了直前に起きた“排ガス規制ショック”
- 15. 取扱説明書に書かれなかった“隠し機能”
- 16. “GT-Rロゴ”に込められた意味
- 17. 最終生産台数“4,000台”の謎
- 18. マニア垂涎の“オプションキット”
- 19. “R32 GT-R”が後のR33/R34へつなぐ架け橋に
- 20. 30年を超えた今も色褪せない理由
- おわりに
はじめに
「ハコスカ」「ケンメリ」に続き、1989年にデビューしたR32型スカイラインGT-R。通称“ゴジラ”の異名を持ち、日本のスポーツカー史に革命を巻き起こした一台です。本記事では、その誕生前夜から量産までの知られざる開発秘話を、海外Wikipediaなどを参照しつつ、エモーショナルかつトリビア満載でお届けします。
1. “ゴジラ”の名付け親は英国の雑誌編集者
-
デビュー直後、英国の自動車雑誌『CAR』誌が「Godzilla」(ゴジラ)と呼んだのが由来。
-
圧倒的な速さと圧力感を「日本の怪獣」と評した鋭い比喩が、瞬く間に定着しました。
2. 開発プロジェクト名は「PGC10」
-
開発責任者たちの内部コードネームは「PGC10」。
-
先代R31の改良型ではなく、完全新設計としてスタートした証です。
3. 伝説のRB26DETTエンジン誕生秘話
-
2.6LツインターボのRB26DETTは、もともと航続性能とターボラグ軽減を両立させるために設計。
-
セラミックタービンホイールの試作に挑戦したが、量産コストの高さから泣く泣く断念。
4. “ハイブースト”の誕生は社内ライバル対決から
-
GT-R開発チームとU12シーマ開発チームの小競り合いがきっかけに。
-
「うちの4WDはパワーが足りない!」という挑発を受け、GT-Rチームがターボ圧を0.3bar向上させたと言われています。
5. フルタイム4WD「ATTESA E-TS」の裏側
-
前後トルク分配を0→50:50まで可変する先進システムは、もともとトラクション不足対策として輸送トラック用に研究された技術がルーツ。
-
R32用にチューニングを重ね、「熱いコーナーでもグイグイ曲がる」特性を実現。
6. 軽量化のための“ウィンドウテスト”
-
ガラス厚を1.9mm→1.7mmへ微調整。ただし安全基準を絶対に満たすため、何度も衝突試験をクリア。
-
その結果、車両重量は先代比でわずか20kgしか変わらなかったものの、ボディ剛性は大幅にアップ。
7. “カーボン”流用の苦悩と栄光
-
本格的なカーボンパーツは高コストゆえ量産には不向き。
-
そこで一部モータースポーツパーツのみカーボン製を採用し、公道用は強化プラスチックで代用。
8. ピットロードからフィードバックされたエアロデザイン
-
JTCC(全日本ツーリングカー選手権)参戦用マシンのエアロパーツが開発車両の風洞実験データにフィードバックされ、ノーマル車にも採用。
-
ノーズ形状の微妙な“えぐり”が、高速安定性に大きく寄与。
9. “セミセルフレベリング”サスペンションの試作
-
乗り心地とコーナリング性能を両立させるため、油圧バランスを自動補正する構想があったものの、最終量産モデルでは「コスト面」により断念。
10. 開発スタッフの愛機は「初代GT-R」だった!?
-
プロジェクトリーダーの吉田氏は、プライベートでハコスカGT-Rを所有。
-
常に「我々もこのレベルに戻せるか?」という自問自答から開発がスタートしたと言われています。
11. 海外テスト走行で露呈した“寒冷地問題”
-
北欧・スウェーデンでのテスト中、冷間時のターボラグが顕著に。
-
そこでオイルラインとヒーターラインのリパイピングを行い、低温でもスムーズな立ち上がりを実現。
12. “電子制御”4WDのチューニング秘話
-
ECUマップは日本と欧州で別チューン。日本仕様は高速安定重視、欧州仕様はワインディングロード向けにセッティング。
13. サーキットのフィードバックが市販車に直結
-
富士スピードウェイでの開発走行中、テストドライバーが「もっとリニアに曲がりたい」と要求。
-
ターンイン域のレスポンスを向上させるため、リアサスジオメトリーを見直す大改修が行われました。
14. 開発終了直前に起きた“排ガス規制ショック”
-
当時の排出ガス基準強化で、最終検証中にトルク低下が発覚。
-
排ガス再循環システム(EGR)の最適化により、パワーをほぼロスなくクリア。
15. 取扱説明書に書かれなかった“隠し機能”
-
独自のテスター診断コードを入力すると、センターデフのロック率調整データが参照可能。
-
一部マニアしか知らない“裏メニュー”として今も伝説に。
16. “GT-Rロゴ”に込められた意味
-
「R」はRacing、「GT」はGrand Touringの意味合い。
-
エンブレムは赤い「R」の文字だけ若干高低差をつけ、スポーツの鋭さを象徴。
17. 最終生産台数“4,000台”の謎
-
国内向け約3,000台、輸出向け約1,000台。
-
当初は5,000台を想定していたが、部品供給の都合とコスト圧縮で最終的に4,000台に。
18. マニア垂涎の“オプションキット”
-
NISMO製LSD、専用マフラー、専用ECU。
-
製造数が極めて少なく、現在ではオークションで一式数百万が当たり前に。
19. “R32 GT-R”が後のR33/R34へつなぐ架け橋に
-
R32で確立したATTESAやRB26DETTは、次世代へ受け継がれ、GT-Rブランドの根幹に。
-
当時の失敗や成功が、後継モデルの信頼性向上に直結しました。
20. 30年を超えた今も色褪せない理由
-
“技術の結晶”であり、古さを感じさせない基本設計の妙。
-
今なおサーキットやワインディングでゴジラサウンドを響かせる姿は、永遠のトリビアです。
おわりに
R32型スカイラインGT-Rは、開発陣のプライドと技術力の粋を結集した一台です。神話級のRB26DETTエンジン、先進のATTESA E-TS、そして“ゴジラ”の称号。30~50代のクルマ好きなら心が震える逸話ばかり。もしあなたがこの愛しきハイパフォーマンスマシンに乗るチャンスがあるなら、ぜひその血湧き肉躍る開発秘話を思い浮かべながらハンドルを握ってみてください。次世代のGT-Rへと繋がる“原点”を、五感で味わうことができるはずです。
💡関連動画💡