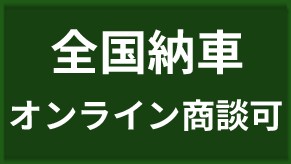はじめに
日産GT-R R35。その名前を聞くだけで、30〜50代のクルマ好きは心がざわつくはずです。R32から続く「GT-R」の血統を受け継ぎながらも、R35は従来の「スカイラインGT-R」とは一線を画した存在として誕生しました。開発の舞台裏では、従来ファンからの反発や、グローバル展開を前提とした野心的な挑戦があり、「スーパーコンピューターを駆使したスーパーカー」という異名を背負うまでの軌跡が刻まれています。
今回は海外Wikipediaを参照しつつ、開発現場のトリビア・逸話・おもしろエピソードを交え、マニアックかつエモーショナルにR35の誕生秘話を解き明かします。

1. 「スカイライン」の名を外した衝撃
-
2001年のコンセプトカー「GT-R Concept」を皮切りに、新型GT-Rは「スカイライン」の冠を外す方針で開発が進められた。
-
世界戦略車として「NISSAN GT-R」として独立した背景には、日産再建を主導したカルロス・ゴーンの判断がある。
-
伝統の名を外すことは社内でも議論を呼び、「本当にGT-Rなのか」という問いが常につきまとった。
2. 「誰でも速く走れる」思想
-
開発総責任者・水野和敏は「プロドライバーだけでなく、誰が運転しても同じように速いクルマ」を掲げた。
-
そのために採用されたのがアテーサE-TS四輪駆動システムと電子制御トランスミッション。
-
当時としては異例の「電子デバイス全盛」の思想に、保守的なファンからは「機械任せのクルマ」と批判もあった。
3. ニュルブルクリンクでの熾烈な開発合戦
-
R35開発において、ニュルブルクリンク北コースは「第2の本社」とも言える存在だった。
-
初期の開発テストではポルシェ911ターボやGT3をターゲットに設定。
-
2007年、量産車最速記録となる7分38秒54を叩き出し、世界を驚愕させた。
-
しかしポルシェ側が「タイヤが市販品でない」と抗議するなど、ライバルとの因縁も絶えなかった。
4. VR38DETTエンジンの秘密
-
3.8L V6ツインターボ「VR38DETT」は、一基一基が匠による手組み。
-
エンジンビルダーは「匠」と呼ばれ、名前入りプレートが貼り付けられる。
-
この“人の手の温もり”が、電子制御に支配されたR35に魂を吹き込んでいる。
5. デザインと空力のせめぎ合い
-
R35の外観は「機能が形を決める」という思想。
-
0.27という低Cd値と強力なダウンフォースを両立。
-
初期デザイン案はよりスリムだったが、冷却性能や空力のためにボディは大型化していった。
6. 「プレイステーションで育てる」戦略
-
日産はソニーと協力し、「グランツーリスモ」にR35を発売前から登場させた。
-
ゲーマーがバーチャルでGT-Rを体験し、そのまま実車購入へつなげる狙い。
-
この“デジタル×リアル”戦略は世界的に話題となり、若い世代に強烈な印象を残した。
7. 世界市場と法規制との戦い
-
R35は北米・欧州・中東といった主要市場を狙い、法規や燃費規制への対応が必須だった。
-
特に北米の排ガス規制をクリアするため、電子制御の綿密な調整が繰り返された。
-
その結果、スーパーカーでありながら日常使用に耐える信頼性を獲得。
8. 庶民のスーパーカーを目指して
-
フェラーリやランボルギーニよりも「安価」でありながら、同等の性能を狙った。
-
海外メディアは「ポルシェキラー」「ジャイアントキラー」と評した。
-
一方で価格は年々上昇し、当初の「誰でも手に届く」路線から離れていったことにファンは複雑な感情を抱いた。
9. マイナーチェンジで進化し続ける哲学
-
R35はフルモデルチェンジせず、2007年から現在に至るまで改良を重ねる方式を採用。
-
毎年のように足回り、ECU、内装がアップデートされ、熟成のプロセスそのものが“R35の物語”となった。
-
これはポルシェ911の進化手法を意識したとも言われる。
10. 開発チームのプライドと葛藤
-
「電子制御に頼りすぎ」との批判に対し、開発陣は「人間の限界を超えるための技術」と反論。
-
当時の水野和敏は「R35は神の領域に挑むクルマ」と公言。
-
この言葉はファンの間で賛否両論を呼び、今も議論され続けている。
まとめ
GT-R R35は単なるスーパーカーではありません。それは伝統を受け継ぎながら、常識を打ち破るために生まれた反逆児です。スカイラインの名を外した勇気、ニュルブルクリンクでの激闘、電子制御と匠の手仕事が融合したエンジン。
その開発秘話は「神をも超える」というキャッチコピーに象徴されるように、時代に挑戦した物語そのものなのです。
💡関連動画💡