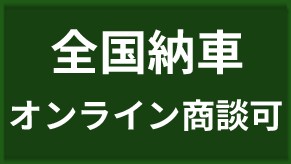「神話の継承者」は、戦いの中で評価を覆した
1995年1月。BNR33スカイラインGT-Rがデビューした瞬間、世界中のGT-Rファンはある“宿命”を思い出した。
──「R32の29戦29勝」。
1989年の復活とともにツーリングカーレースを席巻したR32は、**「Godzilla」**の名で恐れられる存在となり、GT-Rというバッジに“勝たなければならない”という宿命を刻み込んだ。
だが、その神話の影はあまりに大きかった。
R33は登場当初、「重い」「デカい」「鈍い」と批判され、R32ほどの熱狂を得られなかった。しかし、真の評価はサーキットという戦場でこそ語られる。R33は、その“重さ”を武器に変え、冷静で圧倒的な勝負強さを見せつけることになるのだ。

I. グループA終焉の後──R33の戦場は国内だけではなかった
1993年、R32が無敗神話を築いた**全日本ツーリングカー選手権(JTC)**が終了。
その後継となったのは、全日本GT選手権(JGTC)──現在のSUPER GTの前身である。
この新シリーズは、純粋な市販車ベースのGTカーをベースに高度な改造を認めるレギュレーションで、かつての「グループAマシン」とは性格が大きく異なっていた。
日産はこの新時代の戦場に、R33 GT-Rを送り込むことを決意する。
R33はもはや「ストリートカーの延長線」ではなく、戦うために磨かれたGTカーだった。専用ワイドボディ、軽量化されたボディパネル、ブレンボ製ブレーキ、そして熟成を極めたRB26DETT──そのすべてが“レースのためのGT-R”として仕立てられていた。
II. JGTCデビュー戦──“重量級”の反逆
1995年、R33 GT-RはJGTC GT500クラスに投入された。
初陣は鈴鹿GT 300kmレース。ライバルは、NSXやスープラといった新時代のGTマシンたち。R33は「1,340kg」という重量で不利と見られていたが、その見方は一瞬で覆された。
この年、NISMOが投入したカルソニックGT-R(#12)とユニシアジェックスGT-R(#1)は、デビューシーズンから圧倒的な速さを発揮。特に#12は岡山、SUGOで連続優勝し、初年度からチャンピオン争いに加わる大健闘を見せた。
重量級のR33が、テクニカルなサーキットで軽量なNSXを抑え込んだ理由は、圧倒的なトラクションと安定性だった。R33の長いホイールベースと高剛性ボディは、コーナー出口でのパワー伝達に優れ、立ち上がり加速でライバルを圧倒したのだ。
「R33は一見鈍重だが、乗ってみると全く違う。アクセルを踏んだ瞬間、地面を掴んで前へ飛び出すような感覚だった。」
──星野一義(カルソニックGT-Rドライバー)
III. 激戦の1996年シーズン──王者争いの最前線へ
1996年シーズン、R33 GT-Rはさらなる進化を遂げて戦場へ戻ってきた。
エアロダイナミクスが見直され、冷却性能も向上。車重は前年比で約30kg軽量化され、RB26DETTも400ps以上に達していた。
この年、#1 ユニシアジェックス GT-R(影山正彦/エリック・コマス組)はSUGO、TI英田、富士で優勝し、シーズン3勝を記録。最終戦までトヨタ・スープラと王座を争う死闘を演じた。
惜しくもチャンピオンは逃したが、年間ランキング2位という堂々たる成績を残し、R33が“R32の影”から抜け出したことを世界に知らしめた。
IV. 欧州への挑戦──ル・マン24時間とスパ・フランコルシャン
R33の戦いは国内だけでは終わらなかった。
1995年、日産はル・マン24時間レースへの復帰を決断し、R33をベースにしたスカイラインGT-R LMを製作する。
LM仕様は公道用R33のシルエットを残しながらも、ワイドボディ化・車高の極端な低下・空力の徹底追求が施された“別物”だった。
心臓部は信頼性を重視したRB26DETTで、約600psを発揮。駆動方式も4WDからFRに変更され、耐久レースに最適化された。
1995年のル・マンでは#22が総合10位、GT1クラス5位で完走。翌1996年も参戦し、信頼性の高さを証明した。
また同年、スパ・フランコルシャン24時間レースにも挑戦し、総合4位入賞を果たしている。
「GT-R LMは、スカイラインの魂を持ったル・マンカーだった。日本のGTカーがここまで戦えるとは誰も思っていなかった。」
──『AUTOhebdo』1995年ル・マン特集より
V. ニュルブルクリンクの衝撃──8分1秒15の真実
R33が世界の評価を変えたのは、レースだけではない。
1995年、開発陣はニュルブルクリンク北コースで量産車テストを行い、8分1秒15という驚異のラップタイムを記録した。これは当時、ポルシェ911ターボに並ぶ世界最速級の記録である。
この結果は欧州メディアを驚愕させ、「重量級の日本車がニュルでここまで走るとは」と絶賛された。
このタイムは、R33の電子制御4WD「ATTESA E-TS Pro」とアクティブLSDがもたらした圧倒的な安定性と、空力で磨かれた高速域の挙動があってこそのものだった。
「R33はただのGTカーではない。“レースから生まれたロードカー”という言葉が最もふさわしい。」
──ドイツ誌『Sport Auto』1995年試乗記
VI. プライベーターの戦い──世界各地で生まれた“もう一つのR33伝説”
R33はワークスだけでなく、世界各地のプライベーターたちにも愛された。
オーストラリアでは、1990年代後半の耐久シリーズにR33が出場し、名門Gibson Motorsportが手がけたマシンが注目を集めた。
また、ニュージーランドのGT選手権やイギリスのクラブマンレースにもR33は姿を現し、強力な直6ターボと電子制御4WDの組み合わせが「チューナーの理想」として支持された。
チューニングカーの世界でも、R33は“最強のベース”と呼ばれ、800ps級のドラッグ仕様やタイムアタック仕様が登場。
「R33は重い」という常識は、やがて「重いからこそ踏めるGT-R」という再評価へと変わっていった。
VII. “橋渡しのGT-R”が残した遺産
JGTCやル・マンでの実績、そしてニュルでの衝撃的な走り──それらはすべて、R33が「単なる後継車」ではなく、「GT-Rを次の時代へ導く存在」であったことを証明している。
事実、R34やR35が世界で戦えるGTカーとして完成度を高められたのは、R33が積み重ねた戦いの経験と技術の蓄積があったからだ。
「R33がいなければ、R34はここまで完成度の高いマシンにはならなかっただろう。」
──元GT500チーフエンジニア・伊藤修一
終章:「誤解された名機」はいま、伝説へと昇華する
デビュー当時、R33は「R32の影」と戦い続けた。だが、戦場で積み上げた実績がその評価を覆した。
JGTCでは複数の勝利と年間ランキング上位を獲得し、ル・マンでも欧州GT勢と互角に渡り合い、ニュルでは世界最速級の称号を手にした。
R33は“派手さ”ではなく、“実力”でGT-Rの名を刻んだ存在である。
それはまるで、喧騒の中で黙々と剣を研ぎ続ける戦士のように、静かで、強く、美しい戦い方だった。
そして今、30年の時を経て多くのGT-Rファンがこう語る。
──「R33こそが、GT-Rを“伝説”から“世界基準”へと進化させた存在だった」と。
💡関連動画💡