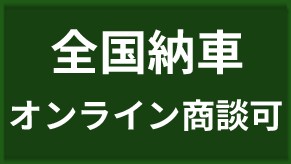「ストリート生まれ、サーキット育ち」──R35が背負った宿命
2007年、GT-Rの名を冠した新たなマシンが誕生したとき、誰もがそのポテンシャルに息を呑んだ。
だがこのクルマが本当に“本物”であることを証明するのは、スペック表でもカタログでもない。
それはただひとつ──サーキットという戦場だ。
R35 GT-Rの開発陣は当初から明確に語っていた。
「我々はサーキットで勝つためのクルマを作っている。量産車であっても、ライバルはレーシングカーだ。」
この言葉通り、R35は市販車としての枠を超え、世界各地の耐久レースやGT選手権で爪痕を残す存在となった。
ここから先は、その知られざる“闘いの記録”である。

I. GT500での衝撃デビュー──「ストリートマシンが本気を出すとこうなる」
R35が初めて公式レースの舞台に姿を現したのは、2008年のSUPER GT GT500クラス。
前年までR34時代の直系モデル「Z33フェアレディZ」で参戦していたNISMOは、新たな戦闘機としてR35の名を冠したマシンを投入した。
このマシン、見た目こそGT-Rだが、中身は完全なレーシングカー。
カーボンモノコック、ドライサンプV8、ミッドシップレイアウト──まさに**“GT-Rの皮を被ったプロトタイプ”**だった。
2008年開幕戦の鈴鹿。デビュー戦でいきなり1-2フィニッシュを飾り、GT-Rは国内レースシーンを震撼させた。
この年、NISMOはドライバーズランキング2位・チームランキング1位を獲得し、「GT-R=勝てるマシン」という印象を一気に植え付けたのである。
「GT-Rは一夜にしてGT500の主役になった」
──日本のモータースポーツ専門誌『Auto Sport』
その後もGT-RはGT500クラスで常にトップ争いを繰り広げ、2011年、2012年、2014年、2015年、2020年と複数回のシリーズチャンピオンを獲得。
ストリートカー由来の名を背負いながら、レース界の頂点を取り続ける姿は、まさに“GT-R哲学”の体現だった。
II. ヨーロッパ耐久レースへの殴り込み──「未知なる敵地で勝つ」
日産の野望は国内だけにとどまらなかった。
R35は2009年、ついに欧州耐久レースの聖地へと挑戦を開始する。
舞台はドイツ・ニュルブルクリンク24時間レース──量産車ベースのマシンが己の信頼性と速さを競う、過酷な耐久戦だ。
デビュー戦となった2009年、GT-Rは「SP8Tクラス」にエントリー。
マシンは市販モデルをベースに安全装備と耐久パーツを加えただけの“ほぼストック”状態だったが、過酷なレースを総合13位/クラス1位で完走。
初参戦でのクラス優勝という快挙を成し遂げ、欧州メディアを驚愕させた。
“The Japanese giant has arrived, and it means business.”
(日本の巨人がやってきた。本気で勝ちに来ている)
──独『Auto Bild』誌(2009年)
その後、GT-RはNISMOと共に改良を重ね、2014年にはGT3マシンとして本格参戦。
「NISMO GT3」はFIA GT3規定に準拠し、世界中のチームが購入して参戦可能な“カスタマーレーシングモデル”として登場した。
III. GT3の主役へ──“顧客チームでも勝てる”思想
GT3マシンとしてのGT-Rは、欧州のブランパン耐久シリーズやBritish GT選手権などで輝かしい実績を残すことになる。
特筆すべきは2015年。
イギリスの「RJN Motorsport」がGT-R NISMO GT3でブランパン耐久シリーズ・プロアマクラス年間チャンピオンを獲得。
この結果は、ワークスではないプライベーターチームがGT-Rで勝利を収めた点で大きな意味を持っていた。
“GT-R has proven that you don’t need to be a factory giant to win.”
(GT-Rは、勝つためにワークスである必要はないと証明した)
──英『Autosport』
また、オーストラリアの伝統レースバサースト12時間耐久(Mount Panorama)では、2015年にR35が総合優勝。
ドライバーは元F1ドライバーの千代勝正らが務め、最終ラップまでの激戦を制しての勝利だった。
この勝利はGT-R史上でも特筆すべき瞬間であり、「日本車が欧州・豪州のGTレースで勝てる」ことを世界に知らしめたのだ。
IV. アメリカへの挑戦──IMSAとPWCでの闘い
GT-Rはアメリカ大陸にも足跡を残している。
2012年から2016年にかけて、**Pirelli World Challenge(PWC)**にGT3仕様で参戦し、スプリントレース形式で激戦を展開。
2015年にはジョニー・オコーネル(キャデラック)ら強豪を相手に表彰台争いを繰り広げ、北米ファンの記憶に強烈な印象を残した。
さらにIMSA(インターナショナル・モータースポーツ・アソシエーション)の一戦にもスポット参戦し、アメリカ市場でもGT-Rの名を広めていく。
直線ではコルベットやViperと互角、コーナーでは911 GT3 Rと渡り合うその姿は、「日本製GT3マシンが欧米の牙城を切り崩す」瞬間そのものだった。
V. ニュルブルクリンクの記録と誇り──“最速の量産車”の証明
R35のレース実績を語る上で、やはり欠かせないのがニュルブルクリンクでの量産車タイムである。
2007年の初期型が7分38秒を叩き出したのは有名だが、進化を続けたGT-Rは2013年、NISMO仕様で7分8秒679という驚異的な記録を樹立した。
これは当時の市販車最速クラスのタイムであり、918スパイダーやラフェラーリといったハイブリッドスーパーカーと並ぶ数字だった。
“It’s not just fast for a Japanese car. It’s fast, period.”
(“日本車として”ではない。ただ“速い”のだ)
──米『Road & Track』
GT-Rは単にレースに勝つだけでなく、「市販車の性能で世界一を狙う」という日産の哲学を、数字という形で証明してみせたのだ。
VI. “進化し続けるレーサー”──R35が残した戦いの軌跡
2020年代に入っても、GT-Rは進化を止めていない。
最新のNISMO GT3は空力と冷却性能が大幅に改善され、ブレーキやECUも最新世代へとアップデート。
世界各地の耐久レースやGT選手権において、今なお“現役”で戦い続けている。
R35のレースヒストリーは、「勝利」という結果だけで測るべきものではない。
市販車の名を背負いながら、欧州の強豪ブランドと真っ向から渡り合い、時に打ち破ってきた**“思想の戦い”**なのだ。
終章:「挑戦することが、GT-Rである」
R35 GT-Rのレース実績は、単なる勝ち負けの記録ではない。
それは、“量産車が世界を相手に戦えるのか”という命題に対する、ひとつの答えだ。
ニュルブルクリンクでの衝撃的なラップタイム。
GT500での圧倒的な存在感。
バサーストでの栄光、GT3での顧客チームの勝利。
そのすべてが、R35というマシンが「ただのハイパフォーマンスカー」ではなく、**“挑戦の象徴”**であることを物語っている。
「GT-Rの本質は、勝つことではない。勝とうとし続けることだ。」
この哲学こそが、R35のすべてのレース実績を貫く一本の矢だ。
そしてそれは、次世代のGT-R──“R36”へと確実に受け継がれていく。