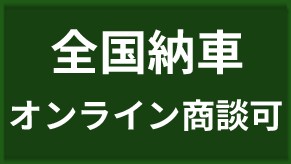「GT-R」という名が海を渡った日
2007年の秋、東京モーターショーのステージに登場した新型GT-Rは、それまでのスカイラインとはまったく別次元の存在だった。
日産が掲げた開発テーマは「世界一のマルチパフォーマンスカー」。それは単なる速さでも、単なる快適性でもない。あらゆる道、あらゆる状況で世界最高を名乗るという挑戦だった。
この“野望”は、瞬く間に海を越えて世界へと広がる。
だが不思議なことに、GT-Rという3文字はどこへ行ってもそのまま通じるにもかかわらず、各国の人々はこのクルマに独自の呼び名を与え始めた。
そこには、それぞれの文化と価値観、そしてGT-Rがもたらした衝撃の大きさが、はっきりと刻まれている。

I. “Samurai Supercar”──ヨーロッパが見た「東洋の叡智」
まずGT-Rが強烈な印象を残したのがヨーロッパだった。
2008年、イギリスやドイツ、イタリアといった自動車文化の本場に上陸したR35は、フェラーリやポルシェといった超一流ブランドと真っ向から肩を並べ、圧倒的なコストパフォーマンスと性能で彼らを脅かす存在となる。
英『CAR Magazine』はデビュー直後の特集でこう評している。
“This is not just a car from Japan. This is a samurai supercar — precision, discipline, and deadly effectiveness.”
(これはただの日本車ではない。サムライ・スーパーカーだ──精密で、鍛え抜かれ、致命的なまでに効果的だ)
「Samurai Supercar(サムライ・スーパーカー)」という呼称は、単なる異国情緒ではなかった。
それは、GT-Rが見せた“日本的な合理性と緻密さ”に対する驚きと敬意の表れだ。
ヨーロッパの多くの高級スポーツカーは、伝統やエモーションを重んじる職人気質の上に成り立っている。
対してR35は、電子制御トルクスプリットやデュアルクラッチトランスミッション、膨大なテレメトリーデータなど、圧倒的な「理詰めの戦略」で勝負を仕掛けた。
ドイツ誌『Auto Bild』は2009年の比較テストでこう記している。
“It feels as if a katana is slicing through corners — sharp, precise, and without hesitation.”
(まるで刀がコーナーを切り裂いていくようだ──鋭く、正確で、ためらいがない)
この“サムライ”という比喩は、R35の本質を見事に言い当てている。
それは力任せの暴力ではなく、技と知恵と精密さで相手を圧倒する存在だった。
II. “The Gentleman Slayer”──アメリカが恐れた「常識破り」
一方で、アメリカでの反応はヨーロッパ以上にセンセーショナルだった。
2009年、北米市場に導入されたR35は、911ターボやコルベットZ06といった大排気量の強豪を次々と打ち破り、「Gentleman Slayer(ジェントルマン・スレイヤー=紳士殺し)」という異名を与えられた。
この呼び名の由来は、アメリカのカーエンスージアストたちが愛してやまない“伝統的な高級スポーツカー”を、GT-Rがことごとく打ち砕いたことにある。
米『Road & Track』誌(2009年7月号)はこう表現した。
“The GT-R humiliates cars twice its price. It’s the Gentleman Slayer.”
(GT-Rは価格が倍するクルマを容赦なく叩きのめす。“紳士殺し”だ)
この「紳士」とは、フェラーリやアストンマーティン、ポルシェといった“伝統的な名門ブランド”のことを指す。
R35はそれらの常識をあっさりと覆し、約8万ドルという価格でスーパーカーを食ってしまったのである。
さらにアメリカでは、「量産車でゼロヨン11秒台」「誰でも300km/hに届く」という現実が、クルマ文化を揺さぶった。
とくにカリフォルニアのストリートシーンでは、「R35が来たらレースにならない」とまで言われ、地下ドラッグレース文化でも一種の“終焉”を告げる存在となった。
III. “Midnight Predator”──中東で語られる「夜の支配者」
中東地域、特にアラブ首長国連邦やカタールなどの富裕層の間でも、R35は熱狂的な人気を博した。
その理由は単純明快──このクルマは深夜のアウトストラーダで最強だったからだ。
ドバイやアブダビでは「Midnight Predator(ミッドナイト・プレデター=真夜中の捕食者)」という呼び名がつけられた。
これは現地のチューニングシーンで、GT-Rがランボルギーニ・アヴェンタドールやブガッティ・ヴェイロンといった数千万円クラスのハイパーカーを夜の高速で“狩っていく”姿に由来する。
現地のオーナー、サレム・アル=ハーリド氏(アブダビ在住)はこう語っている。
「午前2時、シェイク・ザイード・ロードを走ると、GT-Rはまるで獲物を追う狼のようだ。ブガッティの横に並んで、あっという間に前に出る。誰もが“あれはプレデターだ”と言うよ。」
実際、R35は極端な高温環境にも耐えうる冷却性能と、電子制御による高いトラクション性能を備えていたため、砂漠地帯の過酷な条件でも安定した速さを見せつけた。
その姿は、富裕層の“見せびらかすためのスーパーカー”とは一線を画し、「勝つための機械」として畏怖と敬意を集めたのである。
IV. “Digital Samurai”──ハイテクが創る走りの未来像
もうひとつ、ヨーロッパやアメリカの一部メディアで使われた呼称に「Digital Samurai(デジタル・サムライ)」がある。
これはR35が持つ電子制御の先進性と、その根底にある哲学に着目した呼び名だ。
初代モデルから搭載された「ATTESA E-TS」トルクスプリットシステムや、横滑り制御、ローンチコントロール、そしてメーターディスプレイに表示される膨大な走行データ。
これらは単なる電子デバイスではなく、「人間の限界を拡張するツール」として設計されていた。
独『Sport Auto』誌はこう記した。
“GT-R is not a car, it’s a digital katana forged by engineers.”
(GT-Rはクルマではない。エンジニアが鍛え上げた“デジタルの刀”だ)
この呼称は、GT-Rが伝統的な“感性のスポーツカー”とは異なり、科学とロジックの塊として速さを実現していることを見抜いたものだ。
ドライバーの感覚を超える領域に踏み込むその走りは、アナログ時代のマシンでは不可能だった。
V. 呼び名が語る、R35の「本質」
ここまで見てきたように、R35 GT-Rは世界のさまざまな地域でまったく異なる呼称を得てきた。
-
Samurai Supercar(サムライ・スーパーカー) … ヨーロッパが感じた精密さと理性
-
The Gentleman Slayer(紳士殺し) … アメリカが受けた価格破壊と常識崩壊の衝撃
-
Midnight Predator(真夜中の捕食者) … 中東が見た圧倒的な実力と存在感
-
Digital Samurai(デジタル・サムライ) … テクノロジーで速さを切り拓く思想
興味深いのは、どの呼び名も単なる“速い車”ではなく、文化的な意味合いや思想まで踏み込んでいることだ。
つまりR35は、スペックだけで語られるマシンではなく、「世界がそれぞれの価値観で意味づけを行った存在」だったのである。
終章:「GT-R」という名前が、もはや“ジャンル”になった
R35 GT-Rの海外呼称は、単なるニックネームではない。
それは、このマシンが人々の心に与えた衝撃と、クルマ文化に投げかけた問いの数々を象徴する“証”だ。
「GT-Rはクルマではない。概念そのものだ。」
──米『MotorTrend』編集長 トッド・ライナー(2016年)
量産車でありながらスーパーカーを凌駕し、ハイテクの塊でありながら魂を震わせる走りを持つ。
そんな矛盾のすべてが、この3文字「GT-R」に込められている。
そして世界の人々がそれぞれの言葉でGT-Rを呼ぶとき、彼らは無意識のうちにそれを“ひとつのジャンル”として受け入れているのだ。
──GT-R。それはもう、単なる車名ではない。