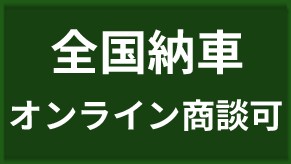1. 失われたGT-Rを取り戻すために
1980年代半ば、日本の自動車産業は空前の繁栄を迎えていた。
だが、日産にはどうしても拭えない“空白”があった。
それは――GT-Rという名が、15年もの間、途絶えていたという事実だ。
最後のGT-R「KPGC110」がわずか197台で生産終了した1973年。
オイルショックと排ガス規制の波が、あの直列6気筒の咆哮を封じ込めた。
以後、GT-Rは社史から消え、日産に残されたのは“いつか必ず蘇らせる”という約束だけだった。
1984年。
その約束を現実に変えようと動き出した男がいた。
**開発主管・伊藤修令(のちのC110・R32開発責任者)**だ。
彼は社内でこう語ったという。
「GT-Rは単なるクルマじゃない。日産の誇りそのものなんだ。
だからこそ、戻ってくる時は“世界一速い量産車”として帰ってこなければならない。」
この瞬間、伝説の再起動ボタンが押された。

2. 技術者たちの理想──“無敗”のストリートマシンを目指して
開発初期に掲げられた目標は、狂気に満ちていた。
──「ポルシェ911ターボを凌駕し、ル・マンでも通用するクルマを作る」。
それが、まだ300馬力自主規制の時代に立てられたゴールだった。
伊藤ら開発陣は、レースで勝てるための市販車を作ることを最初から前提にしていた。
つまり、「市販車ベースのレースマシン」ではなく、
「レースを想定して生まれた市販車」。
GT-Rとは、最初からそのための設計思想だったのだ。
この時、日産社内には二つの意見があった。
「スカイラインの延長線上としてGT-Rを復活させるべきだ」という伝統派と、
「もはや別物として新しいスーパーカーを作るべきだ」という革新派。
結局、伊藤はどちらの道も選ばなかった。
彼が選んだのは“融合”――
スカイラインの血統を受け継ぎながら、未知の技術で未来を切り開くという道だった。
3. RB26DETT──禁じられた領域に挑んだエンジン
R32 GT-Rの心臓、RB26DETT。
このエンジンは、当初からレースで勝つための仕様として開発された。
実際の社内資料では、当初から「Gr.A参戦を想定」と明記されている。
排気量2.6リッター、ツインターボ、直列6気筒。
300馬力自主規制の中で公称280psとされたが、実際には300psを軽く超えていた。
だが真に驚くべきは、高回転域の滑らかさと耐久性だ。
エンジン設計チームを率いたのは、当時の若き技術者・中村史郎(後にGT-Rチーフエンジニア)。
彼は開発ノートにこう記している。
「300馬力という数字に縛られていては、GT-Rは生まれない。
我々の使命は、“数字の上限”ではなく、“可能性の限界”に挑むことだ。」
その思想が、ブースト圧の設定やタービン設計に現れている。
日産は当時、T25型セラミックタービンを選択。
軽量化と応答性を両立することで、わずかなスロットル操作にも“瞬時に反応する”エンジンフィールを実現した。
RB26はその後、チューナーたちの手によって1000psを超える出力を叩き出すことになるが、
それは偶然ではない。
すでに設計段階で“壊れない限界設計”が仕込まれていたからだ。
4. ATTESA E-TSとHICAS──制御技術がもたらした「もう一つの武器」
GT-Rのもう一つの革命が、電子制御四輪駆動システム**ATTESA E-TS(アテーサ・イーティーエス)**である。
このシステムは、当時としては異次元の制御性能を持っていた。
通常走行ではほぼFR(後輪駆動)で走りながら、
トラクションが必要な瞬間に瞬時に前輪へトルクを配分。
電子的な“直感”によって、車体はまるでドライバーの意識を読んでいるかのように旋回する。
開発時のデータでは、1/100秒単位でGセンサーが路面状況を解析。
その結果、コーナリングスピードは当時のポルシェ911を凌駕した。
さらに、**スーパーHICAS(後輪操舵システム)**も搭載。
高速域では後輪がわずかに同方向に動くことで安定性を、
低速域では逆方向に動くことで小回り性能を高めた。
この“多次元制御”こそ、R32が“ただの速いクルマ”ではなく、
**「人間の限界を超えるための機械」**と評された理由である。
5. テストコースでの地獄──開発ドライバーたちの証言
「開発は戦争だった」と語るのは、テストドライバーの加藤博義。
彼はR32のプロトタイプを乗り込み、栃木試験場・富士スピードウェイ・ニュルブルクリンクで徹底的に走り込んだ。
「最初は怖かった。速すぎて、手に負えない。
けれど、走るたびに“人間がマシンに追いつく感覚”があった。」
特にニュルブルクリンクでは、開発最終段階で総走行距離が2万kmを突破。
ブレーキ、冷却、サスペンション、電子制御――
全てがレース本番を想定したチューニングだった。
開発チームは、テスト走行ごとに100項目以上のデータを解析。
ときには1日16時間、夜明けまでコースを走り続けた。
メカニックたちは、エンジンを開けるたびにオイルの匂いで“調子”を感じ取ったという。
「R32は速くなるたびに、人を変えていった。」
──元テストエンジニア・田村宏志(後のGT-R開発責任者)
6. 社内政治とプライド──「予算が尽きても魂は尽きない」
だが、GT-Rの復活は決して順風満帆ではなかった。
当時の日産はバブル景気の中で複数の高級車プロジェクトを抱えており、
GT-Rの開発費は常に“削減候補”に挙げられていた。
開発チームは夜間の社内テストを秘密裏に行い、
他部署の予算を「名目上の研究費」として流用することもあったという。
まさに“地下活動”のような開発の日々だった。
だが、そんな中でも彼らは諦めなかった。
「GT-R」という名を再び冠することが、どれほどの意味を持つかを知っていたからだ。
伊藤はチームに向かってこう言った。
「我々が作るのは、数字のためのクルマじゃない。
誰かの心に刺さるクルマだ。
10年後、20年後に“あれはすごかった”と語られるような、魂の塊を作れ。」
その言葉通り、R32は1989年、ついに完成。
社内テストでは、ゼロヨン4.9秒、最高速度250km/hオーバーを記録。
富士スピードウェイでのタイムは、当時のFIAグループAマシンに迫るものだった。
7. 世界が息を呑んだ瞬間──“再誕”の証明
1989年5月。
ついにR32スカイラインGT-Rが正式発表される。
その姿はシンプルで、無駄がなく、
まるで「戦闘機のような無表情」だった。
だが、ひとたびエンジンに火を入れると、その静寂は豹変する。
6気筒ツインターボの咆哮が地を這い、4輪駆動が地面を掴む。
この“無表情な狂気”こそ、R32の本質だった。
同年、全日本ツーリングカー選手権(JTC)に参戦。
結果、29戦29勝・完全無敗という前人未到の記録を打ち立てる。
これは単なる勝利ではなかった。
それは“開発陣の信念が証明された瞬間”だった。
海外メディアも一斉にR32を取り上げ、
英『Top Gear』誌はこう評した。
“It’s not a car, it’s an engineering manifesto.”
(これはクルマではない。エンジニアリングの宣言だ。)
8. 終章──数字では語れない魂のクルマ
R32 GT-Rの誕生は、技術者たちが自らの信念を証明するための“戦い”だった。
それは経営でも、マーケティングでもなく、
**「理想を具現化するための純粋な情熱」**によって生まれたプロジェクトだ。
このクルマの開発に携わった全ての人が、共通して語る言葉がある。
「R32は、人がクルマを超えようとした瞬間の記録だ。」
その哲学は、R33、R34、そしてR35へと受け継がれ、
今なおGT-RのDNAとして息づいている。
1989年。
日本の技術者たちは、ひとつの“祈り”を金属に込めた。
──「もう一度、世界に夢を見せよう」と。
それが、R32スカイラインGT-Rという名の奇跡だった。
💡関連動画💡