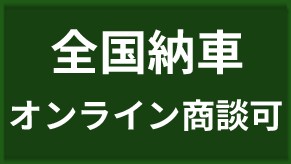はじめに
1995年、R33型スカイラインGT-Rは登場しました。先代R32の圧倒的なレース実績と人気を背負いながら、「次はもっとすごいクルマを」という期待と、「R32を超えるのは不可能ではないか」という重圧。その狭間で生まれたR33は、今なお“過小評価されたGT-R”と呼ばれることがあります。しかしその開発の裏には、ニュルブルクリンクでの徹底テスト、安全性能へのこだわり、そして数々のマニアックな逸話が潜んでいました。
今回は海外Wikipediaの情報をベースに、トリビア・逸話・おもしろエピソードを交え、30〜50代のクルマ好きの心を震わせるエモーショナルな記事を展開します。

1. 「R32の影」との戦い
-
R32がグループAで29連勝という伝説を築いたため、R33開発陣は常に比較対象を背負うことになった。
-
社内の合言葉は「R32を超えろ」。しかしその言葉はプレッシャーとなり、開発者の胃を痛めたと言われる。
-
実際には安全性・快適性を強化するためにボディが大型化し、重量増加を避けられなかった。
トリビア:当初、開発コードネームは「グランドツアラーGT-R」。実は「最強のレースカー」から「万能のスポーツカー」へのシフトが意図されていた。
2. ニュルブルクリンクでの執念
-
R33は歴代GT-Rの中でも初めて“ニュルタイム”を公式に強調。
-
R32の記録を大きく上回り、量産車として初めてニュルで8分切り目前まで迫った。
-
この挑戦が、後に「GT-Rとニュルの切っても切れない関係」を確立するきっかけとなる。
逸話:「ニュルで鍛える」ことは今でこそ常識だが、当時はまだ珍しいアプローチ。開発ドライバーは「ここで速ければ、世界中どこでも通用する」と語った。
3. RB26DETTの熟成
-
エンジンはR32から継続のRB26DETT。しかし冷却系やタービン制御を改良し、信頼性とレスポンスを向上。
-
実はグループNや耐久レースを見据えて、量産仕様でも高負荷連続走行を想定していた。
-
海外メディアは「市販車の顔をした耐久レーサー」と称した。
4. ATTESAとスーパーHICASの進化
-
電子制御4WD「ATTESA E-TS PRO」が採用され、トルク配分に加えアクティブLSDを組み合わせた。
-
コーナー進入から立ち上がりまで、駆動力を自在に変化させる制御は当時画期的だった。
-
四輪操舵システム「スーパーHICAS」もチューニングが進み、高速安定性は歴代随一と評価。
5. セーフティと快適性の強化
-
R33はエアバッグや衝突安全性能を強化。大型化はその副産物でもあった。
-
「最速かつ安全なGT-R」を目指したが、当時の若いファンからは「大きくて重い」と敬遠されがちだった。
-
しかし30年経った今、その安定性と扱いやすさが再評価されている。
6. ニスモ400R――幻の頂点
-
NISMOによるコンプリートカー「400R」は、RB-X GT2エンジンを搭載し400馬力を誇った。
-
生産台数はわずか44台。現在はオークションで数千万円級の価値がつく。
-
海外マニアは「R33の真の姿」と語り、コレクター垂涎の存在になっている。
7. 海外での呼び名と評価
-
豪州メディアはR32に続き「Godzilla」と呼び続けたが、R33には「Fat Godzilla(太ったゴジラ)」という皮肉も。
-
一方でドイツの評論家は「R33は最もバランスの取れたGT-R」と高評価。
-
英国の雑誌『Evo』は「サーキットを知らぬ者が語るには惜しいクルマ」と評した。
8. モータースポーツでの役割
-
R32ほどの圧倒的戦績は残せなかったが、全日本GT選手権(JGTC)や耐久レースで堅実に活躍。
-
特にニュル24時間では、その安定性が武器となり完走率が高かった。
-
「R33は結果以上に、次世代への橋渡し役だった」と日産OBは語る。
まとめ
R33 GT-Rは、R32の伝説とR34の華やかさに挟まれた存在ゆえ「地味」「重い」と言われがちです。しかしその開発秘話を紐解けば、ニュルでの鍛錬、安全性能の強化、NISMO 400Rの誕生といった独自の魅力にあふれていることがわかります。
30〜50代のクルマ好きにとって、R33は青春時代に賛否両論の渦中で見てきた存在。その姿を改めて振り返ることは、クルマの進化と自分自身の記憶を重ね合わせる行為でもあるのです。
💡関連動画💡