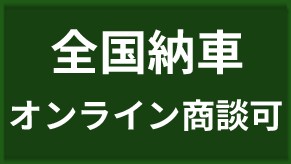「伝説の継承」ではなく「新時代の創造」だった
1999年1月。
「スカイラインGT-R」という名を冠した最後のマシン──BNR34が静かに姿を現した。
R32、R33と続いた黄金の系譜を受け継ぐ3代目GT-RとしてデビューしたR34は、今や伝説の一台として語られる。しかしその誕生の舞台裏は、「単なる後継車」ではなく、「時代と戦うための挑戦」そのものだった。
1990年代後半、自動車業界は大きな転換期を迎えていた。衝突安全や排ガス規制が強化され、環境対応の波が押し寄せる一方で、ハイパフォーマンスカーの存在意義が問われ始めていたのだ。
そんな時代に、日産の開発陣はこう決断する。
「GT-Rは“過去の栄光をなぞる”車ではない。次の時代のベンチマークになる車を作らなければならない。」
こうして、BNR34の開発は“伝説の継承”ではなく“新しい基準”を生み出す戦いとして始まった。

I. プロジェクトR:たったひとつの使命は「究極のRB26を世に出すこと」
BNR34の開発コードは**「Project R」**。
その中心にいたのは、チーフエンジニア・伊藤修一と、R32・R33時代からGT-Rを手掛けてきたエースエンジニアたちだった。
彼らが最初に決めたのは、「RB26DETTをこの世で最も完成度の高い形で世に出す」という目標だった。
R32の登場以来、GT-Rの象徴であり続けた直列6気筒ツインターボは、排ガス規制の影響で消滅が避けられない運命にあった。R34は、RB26最後の花道として開発されたのである。
RB26のチューニングは、すでに限界に近いと考えられていた。しかしエンジニアたちはそこからさらに数百点に及ぶ改良を施す。インテーク経路の改善、インタークーラー容量の拡大、ブースト圧の最適化、そして吸排気バルブの再設計──
結果として純正状態でのレスポンスと耐久性が飛躍的に向上し、チューニングベースとしてのポテンシャルも格段に上がった。
「このエンジンは、ただの動力源ではない。“魂”そのものなんです」
──元RB開発担当エンジニア・西川貴雄
II. 空力とパッケージング──“300km/hの壁”を見据えた設計思想
R34は外観こそR33を引き継いでいるように見えるが、ボディはほぼ新設計だ。
全長を75mm短縮し、ホイールベースを55mm短くした結果、旋回性能と応答性が大幅に向上。重量も50kg以上削減され、運動性能は質的に進化した。
特筆すべきは空力開発の徹底ぶりだ。
R34では日産初のウインドトンネル専用チームが組まれ、前後バランス、車体下の気流制御、リアウイングの角度調整などが細部まで検討された。
特にリアウイングは、量産車としては異例の“角度可変式”。
サーキットではダウンフォース重視、公道ではドラッグ低減というふたつの性格を持たせることに成功している。
さらに、エンジニアたちがこだわったのは300km/hの壁。
量産状態で300km/h超えは不可能という常識に挑み、実際にN1仕様では実測302km/hを記録。空力と冷却、そしてシャシー剛性の総合力で成し遂げたこの数字は、当時の欧州スーパーカー勢と比べても遜色なかった。
III. ATTESA E-TS ProとアクティブLSD──「人間と機械の共同戦線」
R34の走りを根底から変えたのは、電子制御4WDシステムATTESA E-TS Proの進化である。
従来型では前後のトルク配分が「予測」ベースだったが、R34ではヨーレートセンサーと横Gセンサーを統合制御し、ミリ秒単位で駆動力を最適化する仕組みを採用した。
結果、ドライバーが意図するラインを正確にトレースし、アンダーステアやオーバーステアを未然に抑制できるようになった。
さらに、アクティブLSDの制御ロジックも刷新され、トラクションが不安定なコーナー出口でも最適な駆動配分を瞬時に行う。
「GT-Rの4WDは“機械がドライバーを補う”のではなく、“ドライバーと一緒に戦う”ためのものになった」
──元シャシー開発チーフ・高田正志
この制御系の進化は、R34を単なるハイパワーFRベース4WDから、知能を持ったドライビングマシンへと進化させたのである。
IV. サーキットで鍛えられた「公道レーシングカー」という思想
R34の開発チームは、テストコースではなく実戦の現場を開発の舞台に選んだ。
筑波、鈴鹿、富士はもちろん、欧州ではニュルブルクリンク北コースを徹底的に走り込んだ。
開発初期段階から、量産車でありながら「公道で走るレーシングカー」という思想が貫かれていたのだ。
実際、Vスペックではサーキットでの走行を想定し、油温・水温・ブースト圧などが一目で確認できる**マルチファンクションディスプレイ(MFD)**が搭載された。
この機能は、当時の市販車としては完全に“異端”な装備だったが、ドライバーとマシンが“共に戦う”という思想の象徴でもある。
「MFDは飾りじゃない。戦うための情報を伝える計器なんだ。」
──R34開発チーム・電装担当
V. VスペックII、M・スペック、Nur──進化する“完成形”
R34は、登場からわずか4年の間に数々の派生モデルを生み出した。
なかでも重要なのがVスペックII(2000年)、Mスペック(2001年)、そして**VスペックII Nür(2002年)**だ。
VスペックIIではカーボン製ボンネットと専用サスペンションが採用され、軽量化と高剛性化を同時に実現。
Mスペックは「GT-R=サーキットマシン」という固定観念を破り、上質な乗り心地と長距離クルーズ性能を両立した“グランドツアラーGT-R”として登場した。
そして、シリーズの集大成となったのがVスペックII Nür。
エンジンはN1仕様RB26をベースとした特別チューニングで、実測で450psオーバーに達する個体も存在した。
Nurは単なる限定車ではなく、「RB26というエンジンの最終到達点」として、エンジニア全員の想いが込められたモデルだった。
「Nurは“終わり”ではなく、“未来への布石”だった。」
──元GT-R総合開発責任者・伊藤修一
VI. R34が未来に遺した“技術の遺伝子”
R34は2002年に生産終了を迎え、スカイラインGT-Rの時代に幕を下ろした。
だが、その遺伝子は途絶えることなく、R35 GT-Rの開発へと受け継がれていく。
ATTESAの制御思想はR35の電子制御トルクスプリットへと進化し、空力設計の考え方はNISMO GT-Rの空力開発にも活かされた。
何より、「量産車でありながらサーキットを走るために作る」という哲学は、今なおGT-Rの根幹に息づいている。
R34は“最後のRB26”であり、“最後のスカイラインGT-R”であると同時に、次の時代へのスタートラインでもあったのだ。
終章:「伝説」と呼ばれるよりも、「到達点」と呼ばれたい
R34が誕生した1999年は、時代がスポーツカーに逆風を吹かせていた。
だがその中で、日産の開発陣は「伝説を守る」のではなく、「未来に残る基準をつくる」ことを選んだ。
究極まで磨き上げられたRB26、精密な電子制御、空力と冷却の統合設計、サーキットで鍛えられた走り──
そのすべてが結実したR34は、ただの名車ではない。「一つの時代の到達点」として今もなお特別な輝きを放っている。
“あの頃”のGT-Rを知る者は言う。
「R34だけは、数字では測れない」と。
それは最高速や馬力といったスペックの話ではない。
R34は、情熱と執念と技術が結晶となって生まれた最後のピュアGT-R──
その誕生の物語こそが、クルマ好きが今も語り継ぐ「R34開発秘話」なのである。
💡関連動画💡